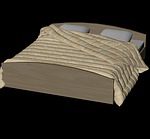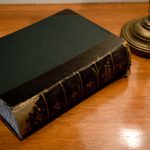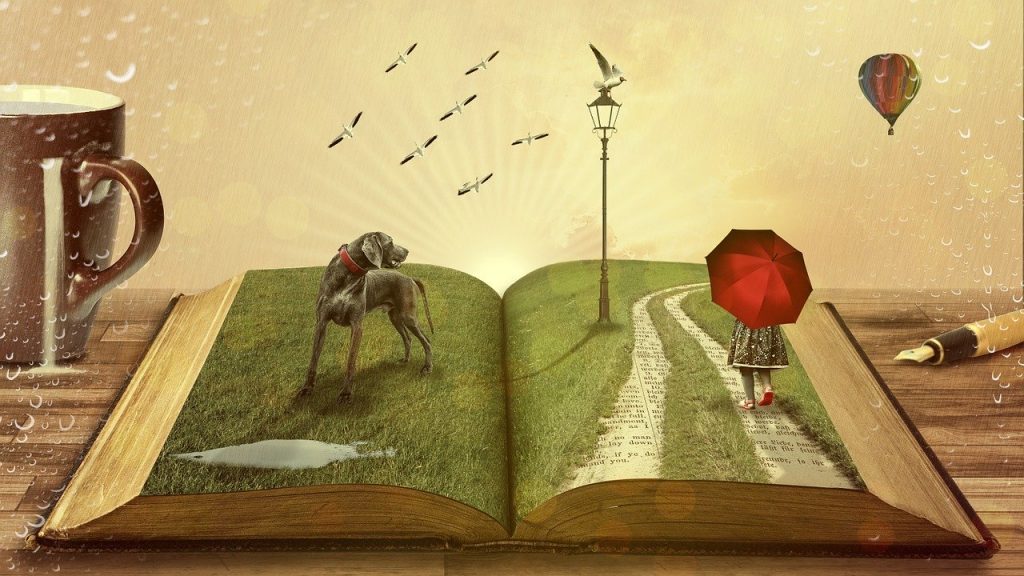
デイサービスに携わるようになって10年、ずっと介護保険に関わっていてもわからないことだらけです。
このシリーズでは介護保険に関わるちょっとわかりにくい法律や制度、関わる行政機関に関して深堀りをしていきたいと思います。
第1回目は介護保険法の成立の過程について見ていきたいと思います。政治的な話も交えて、当時の文献を見ながらまとめて行きたいと思います。
目次
介護保険制度設立への背景
急速な高齢化と措置制度の限界
戦後のベビーブームが終わりを迎えた1950年をピークに出生率は下がり続けるとともに医療の発展による死亡率の低下も相まって、1970年代から日本は高齢化社会(高齢化率7%以上)に突入します。
その後も高齢化率が急増していくことは明らかであるなか、要介護者の顕在化が問題になっていました。
当時の介護は措置制度といい市町村が直接(または委託)サービスを提供していました。
そのため、需要に追いついていなかったり、競争の原理が生まれずにサービスの質が悪かったり、と多くの問題が発生していました。
地方分権化への流れ
介護保険法が成立したのが1997年ですが、同時に地方分権法も制定されています。1990年代は国から地域への権限の移乗の流れが主流となっていました。
介護福祉サービスは地方分権の魁として、1980年代の福祉八法の改正を期に市町村への権限移譲が始まりました。
介護保険の保険者が市町村になるのは自明の理でした。
民間の参加
介護保険制度の一つの特徴として民間の力を大きく使っているという部分もあります。
措置制度のサービスの質は問題視されており、多くの参入のもとで公正な競争下でのサービスの質の向上を狙うという面もありました。
介護手当(介護家族への現金支給)制度を取らなかったのは民間事業者の参入を促すためでもありました。。※その他にも女性を家庭に縛り付けることになるとの批判もありました。
細川内閣国民福祉税の頓挫
細川連立政権家で消費税を7%にして介護費用に当てるという構想がありました。当時から国民の消費税への抵抗感は強く、頓挫する事になりました。
この流れを受けて介護費用は保険制度が取られるという流れが出来上がりました。
介護保険設立までの流れ
厚生労働省内の動き
1989年のゴールドプランが策定され1900年には福祉八法の改正があり、1994年には新ゴールドプランが策定される中で、厚生省は高齢介護サービスの充実化が急務であることを認識していきます。
1994年4月に高齢者介護対策本部(事務次官が本部長)を立ち上げ、専任スタッフを設置し、同年7月には高齢者介護・自立支援システム研究会(座長:大森彌)が設置されました。
この研究会は利害関係者は含まれず、10数名の専門家で構成されました。
介護保険の礎となる①高齢者による選択。②介護サービスの一元化、③ケアマネジメントの確立。④社会保険方式の導入などを提言しました。
この提言はマスコミを通じて世間に伝わり概ね賛同を得ました。
また、首相の諮問機関である社会保障審議会も介護保険制度の設立を提言し、後押しとなりました。
これを受け、1995年2月に利害関係者を含めた議論の場として老人保健福祉審議会(会長:宮崎勇)が設立されました。
老健審には日本医師会、医療保険団体、市町村会、経営者団体などが参加していたため利害関係の調整に時間を要しました。
特に財源の負担に関しては利害関係者が多いため具体的提言を行うことができませんでした。
一方、介護サービスの種類、要介護認定制度、ケアマネジャー制度などの骨格案などの現在の介護保険制度の基本となる制度を生み出しました。
土台ができた今、これ以上は政治マターとなっていきます。
政治に翻弄される介護保険
戦後からの自民党一党政治が終りを迎えた1993年から政治はしばらく合従連衡の時代を迎えます。
一党で政権を維持することができず、連立政権を組むことで政権運営を行っていました。
政権基盤が揺らいでいる政権内での法律成立には政治決定が不可欠です。というのも、法案の内容に国民負担が含まれる介護保険法は政権を崩壊しかねません。
制度の概要は作られたものの、国会に通すためのプロセスは与党に託されたわけです。
介護保険法の土台が出来上がった1996年は自民党・社会党・新党さきがけ(自・社・さ)連立橋本内閣(菅厚相)でした。
当初から自民党は1996年に介護保険法を成立させたがりましたが、反発する主体が2つありました。
それは健康保険法の成立で痛い思いをした市町村と、国民でした。
特に橋本内閣が気を使ったのが、住専処理の国庫負担に怒っていた国民に対する理解です。
新たな保険制度導入による国民負担の増加が政権運営を危うくしかねなかったからです。
選挙を控えた政権は1996年の成立を断念し、翌年の成立のために準備に入ることになります。
1997年となり、与党3党は介護保険制度創設ワーキングチーム(座長:山崎拓)を設けました。
ワーキングチームはまず市町村との対話のため地方での公聴会を各地で行い、様々な意見を聞いて回りました。
菅厚相も積極的に国民の意見を聞くなど政治家が全面に出て政策の不満を聞いて回りました。
その結果、施設系サービスと居宅系サービスの同時開始や都道府県に財政安定化基金を置くことなどを決めました。
こうして市町村と国民の不安を取り除いた介護保険法は1997年の9月に無事成立したのです。
法案成立から制度発足まで
1997年に設立された介護保険法の施工は2000年と予定されていました。この3年間の間も、政治によって介護保険は最後まで揺さぶられました。
政界再編により政権与党にいた社会(社民)党が分裂し民主党に吸収されたり、公明党が誕生するなど大きな動きがありました。
政権を維持するために連立を組まなければならなくなった自民党は最終的に自由党と公明党と連立政権を築きました。
執行部の面々からはこれまで介護保険成立に携わった人物は離れ、むしろ介護保険に反対の立場をとっていた人物が多く採用されました。
中でも費用の税負担を主張していた小沢一郎や亀井静香の主張により、一時は介護保険法施行の凍結論まででました。
しかし、結局は予定通り2000年の施行となったのは介護保険制度の施工を国民が望んでいたからに他なりません。